ワークライフバランスを考える上で大事なのは〇〇

こんにちは
群馬県高崎市の整理収納アドバイザーたなかえりです
先日の総裁選
日本初の女性総裁とし高市早苗さんが選ばれました
高市さんの言葉
「ワークライフバランスという言葉を捨てて、働いて働いて働いてまいります」
今回はこの『ワークライフバランス』という言葉と片付けについて考えてみました
ワークライフバランスの第一歩は、“暮らしの土台”から

「ワークライフバランス」と聞くと、
仕事と家庭の時間の配分や、スケジュール管理を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか
私も以前は、「時間の使い方」こそがバランスの鍵だと思っていました
でも、3人の子を育てる(夫は単身赴任中)暮らしの中で気づいたのです
本当に大事なのは、時間の管理よりも“環境の整え方”だということに
散らかった部屋では、心の余裕は戻ってこない
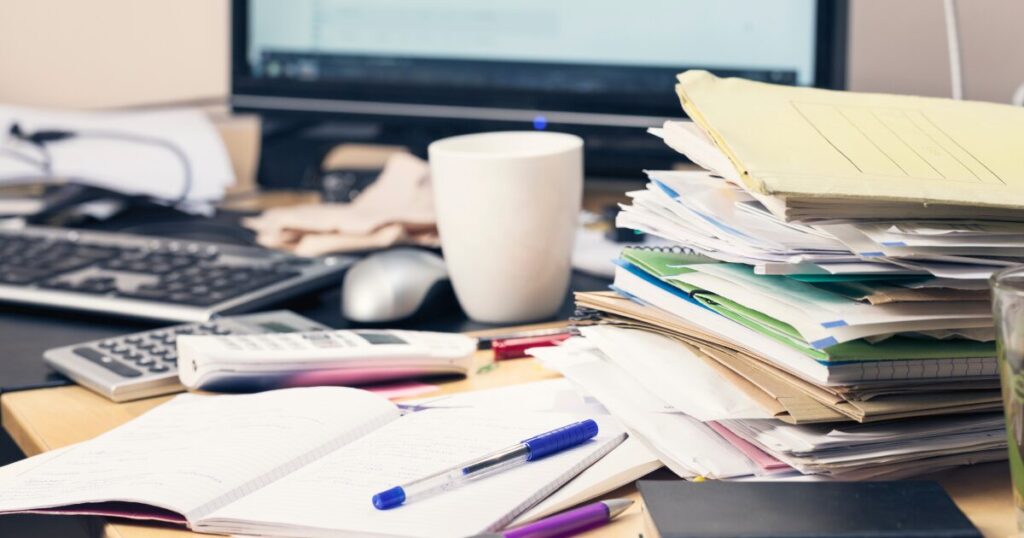
どんなに頑張っても、家の中がごちゃついていたら、
心の余裕はなかなか保てない
片付いていない状態は、実は“時間のロス”の連続なんですよね
探し物、二度買い、家事の段取りのやり直し……
そうした積み重ねが、気づかないうちに私たちの大切な時間を奪っているんです
「頑張っているのに、毎日追われている」
「家にいるのに、休まらない」
そんな感覚を覚えたことがある方も、多いのでは?
家が整うと、“考えなくていい時間”が増える
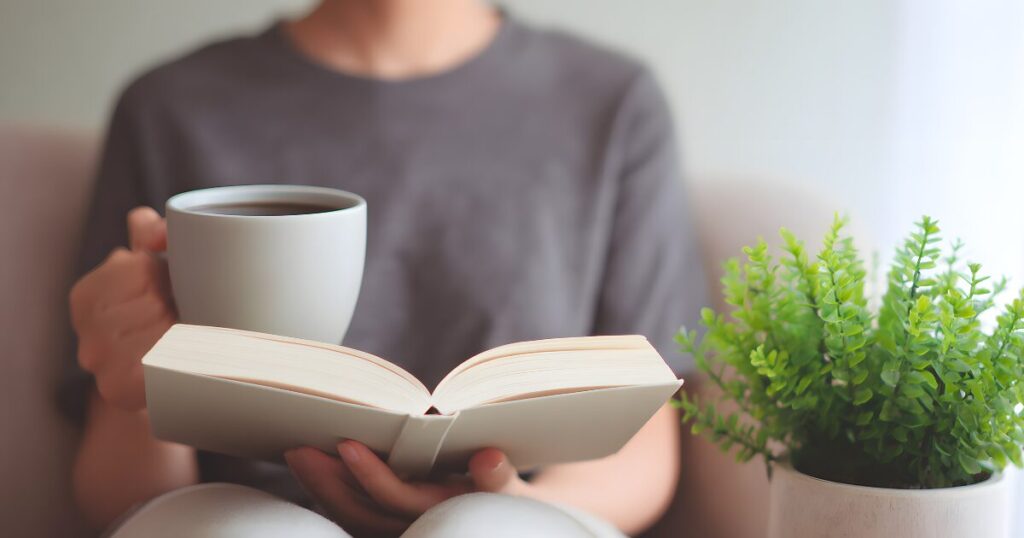
片付けの目的は、見た目をきれいにすることではありません
では片付けの本当の目的は何かというと
考えずに行動できる“仕組み”をつくること
モノの定位置を決めておくだけで、探す手間が減り、
「これどこに置こう?」「どこにしまおう?」と迷う時間がなくなります
子どもに「ママ、あれどこ〜?」と聞かれなくなります
家が整うと、考えなくていい時間が増える
その分、子どもとの会話や、自分のリセット時間が生まれます
私自身、3人の子のワンオペ育児をしながらも、「仕組みで動く部屋づくり」を意識しています
だから、誰かが多少片付けをサボっても、家は自然と回っていく
それが、“整った環境”の力だと思っています
仕組みがある暮らしは、頑張らなくても続く

よく「子どもが小さいから、片付けは無理です」という人がいます
でも実は、小さいお子さんがいる時期こそチャンスです
なぜなら、“仕組み”で動く片付けを取り入れてしまえば
頑張らなくても自然に片付く環境がつくれるから
時間がない人こそ必要なことなんです
「使う場所の近くに収納をつくる」
「家族が”ちょうど良い”適量を決める」
「家族が“戻しやすい”ルールを共有する」などなど
たったこれだけで、毎日の小さなストレスが減っていきます
仕組みが暮らしを回すようになると、家事も子育ても、“気合い”ではなく“流れ”でこなせるようになります
スケジュール帳より、“暮らしの土台づくり”を

ワークライフバランスを整えるために、新しい手帳を買ったり、時間管理アプリを使い始めたり
そうやって“時間”ばかり見直している人、多いのでは?
でも、どんなに予定をうまく組んでも、家が整っていなければ、またすぐに時間は足りなくなってしまう
だから私は、こう考えています
ワークライフバランスの第一歩は、
スケジュール帳より“暮らしの土台づくり”から
家の中が整うと、自分の心も整います
余裕ができると、笑顔が増え、会話も増える
暮らしの土台を整えることは、仕事にも、育児にも、人生そのものにもつながっていると痛感しています
環境を整えることは、心を整えること

「家を整える」というと、“片付け上手になる”とか、“見た目をきれいにする”と思われがちですが、本当の意味は少し違うと思います
それは、自分や家族が気持ちよく過ごせる環境をつくること
そして、その環境があるからこそ、頑張りすぎずに生きられるということ
時間を整える前に、まず“暮らしを整える”
それが、私が今回たどり着いたワークライフバランスの形です
その整え方が分からないんだよ〜
という方はぜひ相談してください